
在学生・卒業生インタビュー
在学生には学生生活の魅力を、卒業生には学生時代の学びが現在の
仕事にどのように役立っているかを語って貰いました
-
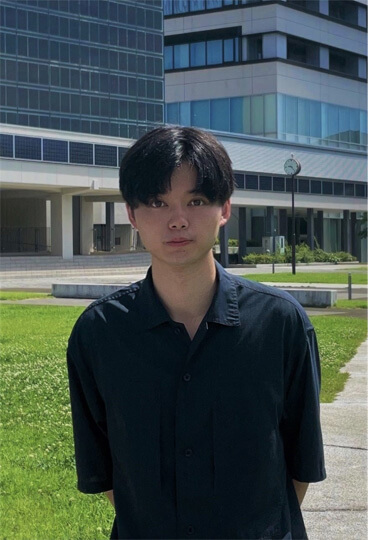
飯塚 凌多さん
2024年度卒業
出身高校:東京都立小平南高校
以下は在学時のインタビューです.経営システム工学科を選んだ理由を教えてください。
高校までに学んできた数学が社会でどのように応用されているのかが気になっていたのが一番の理由です。また、経営システム工学科では数理ファイナンスや金融工学と呼ばれる分野ついて学ぶことができる点に惹かれたことも経営システム工学科を選んだ理由の一つです。
実際に入学してみて、入学前にもっていた学科の印象と違ったところなどはありますか?
入学前は数学やプログラミングに関係する科目が大半を占めているという印象を持っていました。しかし、実際に入学してみると財務会計や法律に関係する授業も多く用意されており幅広い知見を得ることができる点で入学前の印象との違いがありました。
研究室ではどのようなことをしていますか?
数理ファイナンス研究室に所属しています。オプションの価格付けの理論やリスク管理、確率論など研究の基礎について学んでいます。OB、OGとの交流(懇談会、食事会)も活発に行われており、金融業界をはじめとした各業界の動向や詳細など就職活動に役立つ情報を得ることができます。
卒業後の進路についてはどのように考えていますか?
卒業後の進路として金融専門職に就くことを考えています。具体的には証券会社でアナリストとして働くことを目標にしています。そのためには大学院に進学し、より高度な専門知識を身に着けることが重要であると考えています。
日常の大学生活はどのような感じですか?
自宅から自転車で10分ほどかけて登校しています。アルバイトは飲食店や大学内で後輩学生の学習を支援するラーニングサポーター等をしています。通学時間が短いため、空いた時間を資格勉強やアルバイト、レポート等に取り組むことに充てられ有意義に過ごすことができています。
受験を検討している高校生、新入生にメッセージをお願いします。
法政大学理工学部経営システム工学科では、数学、統計学、プログラミングを中心に学びます。これらを応用して実社会におけるランダムな現象を数理モデル化して解析します。また、実際の数値として結果を得るためにシミュレーションをすることで社会や経営における諸問題の解決や最適化する手法について学ぶことができます。そのため、数学やプログラミングが好きでさまざまな社会現象を解析、最適化してみたいという人におすすめです。数理システム、企業システム、生産システム、社会システムの4分野のいずれかを専門とした12の研究室があるため、やりたいことがきっと見つかるはずです。
よくある質問
-
経営システム工学とは何ですか?
経営システム工学科の目的は、「経営」を数理的に理解し、既存のシステムの評価や新しい企画を生み出せる能力を養成することにあります。ここでの経営とは、会社や企業の経営の意味よりもずっと広く、社会の様々な分野における多種多様な意思決定やマネジメント全般のことを指します。
社会のあらゆる組織の経営には、現状を客観的かつ定量的に理解し、新しい活動や事業を計画し、実施・実現することが求められています。このような経営上の問題に対して、数理を基礎として解決を図ろうとする立場を、「経営システム工学」と呼びます。
-
「理工学部経営システム工学科」は「経営学部経営学科」とどこが違いますか?
経営学部では、企業経営にかかわる人達の成功/失敗などの過去の経験を重視していると思います。経験則を蓄積し、議論を通して理論化されることで、企業経営とは何か、どうあるべきかが体系化されると言ってよいでしょう。
これに対して経営システム工学科では、より数学的・工学的にアプローチします。企業組織の中で、特にヒト・モノ・カネ・情報に関する問題を数理的なモデルで表現し、さまざまな手法を用いて、モデルの特性を明らかにしたり、最適な解を見つけたりして、意思決定の補助的道具として用います。数理モデルを利用することの大きな利点は、個人の経験値や技術レベルにかかわらず同一の結果を得ることができ、検証や改良が容易にできる点にあります。
-
授業科目の種類や傾向が多岐に渡っているようなのですが?
経営システム工学科では、社会の様々な問題に対して数理的な解決策を見いだせる技術者の育成を目的としています。分野を大きく「数理システム」「生産システム」「企業システム」「社会システム」の4つに分けた上で、それぞれの特性に合わせた授業科目を配置しています。数学、確率・統計、プログラミングなど、全分野に共通する基盤的な科目は必修または選択必修としていますが、それ以外は自分の興味や将来像に合わせて、幅広い分野の履修ができるように設計されています。
-
学科の定員は何人ですか?
現在の入学定員は80人です。
-
男子学生と女子学生の比率はどの程度ですか?
学年によって変動しますが、女子学生の割合は10〜25%程度です。
-
大学院とはどのようなところですか?
学部は勉強中心の場であり、専門的な内容を理解し、使えるようになることを目指します。対する大学院は研究中心の場であり、これまでに知られていなかった法則を発見したり、新しい技術を生み出せる能力を身に着けることを目指します。